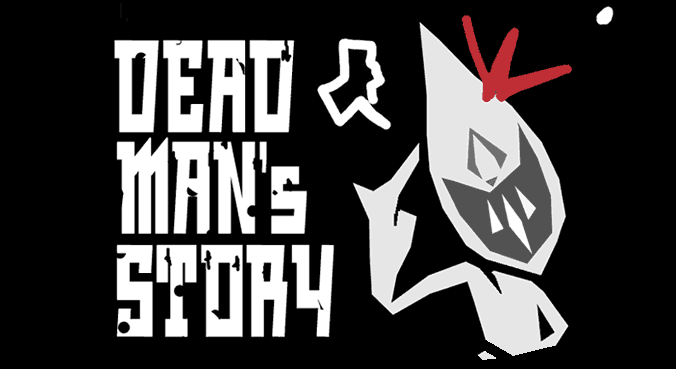 |
08 コンビニエンスストアの窓から漏れた光が、彼の白い体を、 少しだけ黄色に染める。 その艶やかで、潤ったな肌を見て、コンビニエンスストアの店員は 隣の店員の肩を叩き、言った。 「あれ、おでんの玉子みたいじゃね?」 話題を振られたもう一人の店員は、手にした 「うわっ、すげぇ、何だアレ。エッグマン?」 店員の声が大きいせいで、もちろん聞こえた。 いちいち、名刺を出して反論し、逆に笑われたら余計ショックなので DEADMANは、聞こえない振りをして、通り過ぎた。 店内からは、侮蔑の笑い声がまだ、かすかに聞こえていた。 彼は、別のコンビニエンスストアに向かい歩いていた。 本来なら、先ほどの場所で、用事を済ます予定だったが 自分が槍玉に挙げられ、恥ずかしくて入れなかった。 「どうもーエッグマンです@」 そんなことは死んでも言えない。 ただ、彼自身、昔、玉子に自分の顔を描いたことがあるのは、 ここだけの秘密だ。そして、悦に入ったことも。 それは友達がいなかった故の奇行。 遠い夏の思い出。 違和感を感じた。 上を見ると、かすかに人影を感じる。 彼は、急いで、目の前のビルのエレベーターに駆け寄る。 __________飛び降りか? エレベーターは数字は運良く1階を示している。 上矢印のマークをすばやく連打する。 しかし、喜びもつかの間、数字は、1階から2階、3階へと上昇していく __________先に押された・・・。 彼は駈けている。階段を飛ぶように駈ける。 最上階、すなわち屋上までは13階。 随分と長い道のりだ。息を切らすことなく、走り続ける。 何のために? それは、相手を救うため。もし相手が救いを必要としてなくても それはそれで、まぁ、いいかなと彼は思っている。 屋上には、一人の子供がいた。年齢は小学生の高学年といったところ。 気がつかないのか、気づかないのか彼の方を見ようともしない。 「どうしたんだい?」 彼はそっと尋ねた。 「・・・別に」 「だめだよ。危ないよ」 また少年は、振り向かない。ただ、前を見つめたまま何事か呟いている。 別にいいだろ。そんな言葉が聞こえた気がした。 「もう、生きるのをやめるのかい?」 少年は無言だ。彼は頭を回転させ、瞬時に彼の気が変わるような 気の利いた言葉を捜し、続けざまに言った。 「血、ドバドバでるよ」 彼は、自分の馬鹿さ加減をこっそり嘆いた。 「え、ホント?」 __________のってきた。子供は擬音が好きらしい。 「何かあったの?」 「ないよ。ないからつまらないんだ。」 「楽しいことも?」 「余計ないね。」 少し、無言の時間が過ぎた。少年は、いまだ前を向いたままだ。 いつかは言葉が届くのを信じ、彼はまた、話しかける。 「そっか。君の両親は心配しないの?」 「さぁ?お母さんは、いない。それに、お父さんは心配しないよ」 「何でそう思うの?きっと心配してるはずだよ」 「僕のこと嫌いだから」 「絶対に?どうして?」 「しつこいなぁ、毎日毎日、僕の顔を見ると、塾か学校の話しか尋ねないし 塾なんて行きたくないって言ってるのに。 将来がどうだとか、今のうちからどうのってうるさいし、 遅く帰ってきても、謝りもしない。最悪だよ」 続けざまに、少年は、想いを告げる 「それに、ゲームも買ってくれないし、一人で暇だって言ってるのに 友達が羨ましいよ。あんな家なくなればいいのに」 彼にも、少しづつ事情が飲み込めてきた。 さりげなく、少年の会話の聞き役にまわる。 少年がしばらく悩みや想いをぶつけた後で、彼は言った。 「別に、楽しいことなんていくらでもあるよ。探せばの話だけどね」 「ないよ。探すのも面倒だし」 「あるよ。今は見つからなくても近いうちに見つかる。 それに、その気持ちをお父さんに言ってみたら? 「だから言ったって無駄だった」 「なら、もう一度、言ってごらん。それにね、君が 想いを伝えたいなら、会話の主導権を握らないと。 相手が聞いてくること答えるだけじゃなくて、自分がしたいことを 相手に尋ねるんだ。そうしたら、きっといい話し合いができると思うよ」 少年は、無言だ。何も言わない。少し考えているのだろう。 これを好機と考え、彼は続けて話を進める。 「うまくいけばね、ゲームとか余裕で買ってもらえるよ 。一度、試してごらん。それからでも遅くないよ。ほら、今日はもう帰りなよ」 少年は、無言で頷いた。 そして、その表情は、少しはにかんだように見えた。 少年は、ようやく彼の方を向き、何か言いかけたその瞬間。 「うわっ、お前何だよ、何でそんなに白いの、あっち行けよ、行けって」 少年は彼から逃げるように、エレベーターめがけて走る。 少年は化け物にでも合ったかのように、顔を引きつらせ、下矢印の ボタンを連打する。 「あ、あの」 エレベーターは上がってこない。彼はゆっくりと、少年に近づく。 「くるな、くるなって」 少年は待ちきれなかったのだろう、エレベーターに背を向け、 階段の方へ走り、一気に駆け下りていく。 足音が、少しずつ遠くなり、数分もしないうちに消えた。 彼は、追おうとはしなかった。 立ち止まってくれないのを知っているから。 また、何段かの階段を上り、少年がさっきまでいた場所へ向かって歩く。 上から覗いてみても、少年の姿はもう、見えない。 __________あの時も、僕は怖がられてたなぁ 一縷の風がそっと彼の頬を撫でる。その風に感化されたのか 彼は自嘲的に笑い、 「僕が、初めて飛んだのは、ここだったんだよ」 彼は、誰に言うわけでもなく、そっと呟いた。 BACK TOP BBS |